週末は子どもの幼稚園のパフォーマンスデーがありました。
自分の夢を英語でスピーチしたり、劇をやったりしていました。
1年前のパフォーマンスデーでは、みんながダンスを踊っている間、ずっと座ってしました。
その時は、妻と一緒に苦笑いをしながらも、
娘には「嫌がらずに、ちゃんと幼稚園のパフォーマンスデーに行けて、さらにちゃんと前に出れたことがすごいよ!」
といい所を伝えるようにしていました。
それに比べると、今年のパフォーマンスデーは一人で英語でスピーチも出来て、しっかりと立ってられて、劇もみんなと一緒に楽しそうにしていました。
子どもの成長をした姿に感動をして、自分も勇気をもらうことができました。
スピーチでは、
“I want to be a teacher ,because I like study”と言ってたのが、意外でした
しかし私も本を通して勉強をして、それを伝えることが好きなので、同じ夢を持っているのかなと思いました。
※ちなみに画像はパフォーマンスデーの写真ではなく、週末に行ったバンコクのフアムム・マーケットのサタニーミーホイのムキムキの女装したお兄さんが盛り上げてくれるレストランの写真です。
最初はお店に入ることを嫌がっていた娘も、終わったころには楽しんでおり、娘の誕生日パーティーはピンクのお兄さんがいるところでやりたいと言ってました笑
ひと言
2025年2月2週目
2月14日はバレンタインデー
ネットで検索すると、タイのバレンタインデーは男性から女性にプレゼントすると書いてあるのですが、ローカルのスタッフに聞くと、特に性別での縛りはなく、家族や上司、部下に日頃の感謝を込めてプレゼントをあげるようです。
その情報を聞いて前日に急遽フジスーパーに行きました。
私が3月末までに本帰国をするという連絡事項があったため課内会議を急遽ひらきました。
久しぶりに課員と対面をすることになり、新鮮な気持ちになりました。
今まではOne on One meetingで一人一人と対面することは何度かあったのですが、
課内会議は自分が赴任した時の自己紹介ぶりだったことを思い出しました。
定期的に課員が集まって顔を合わせることや、
日頃の感謝を込めてお土産やお菓子などを配ることも、課内のコミュニケーションが活性化されるのでいい方法だなと言うことを学びました。
マネジメントや人間関係、信頼関係、心理的安全性の構築方法など色々と学べております。
「どうせ死ぬんだから、好きなことだけやって寿命を使いきる」和田秀樹さん著書より
◆極上の死に方
極上の死に方とは、つまるところ死ぬ間際まで「極上の生き方」を追い求めるということ。
人生の幕が下りるまで、自分らしく生き抜くということ
死を意識した方が、「生」を楽しもうという気になれる。
自分の心と体の声をしっかり聴いて、10年後に生きていられるかどうかわからないから、やっぱり旅行に行こうとか、これだけはやっておこうとか、そういうふうに考えると、死ぬまでの生活をより濃厚に楽しめる。
ご 極上の死を迎えるために、自分が納得のいく生き方を貫き通す
く 苦しいことやわずらわしいことは、できるだけやらない
じ 自由気ままに暮らす。我慢すると心身ともに老化が加速する
よ 要介護になったら残された機能と介護保険をフルに使い、人生を楽しむ
う うかつに医者のいうことを信じない。治療も薬も選ぶのは自分
の 脳と体を使い続けて、認知症と足腰が弱るのを防ぐ
し 死を恐れれば恐れるほど、人生の幸福度は下がる
に 人間関係が豊かなほど老いは遠のく。人づき合いが億劫になったらボケる
か 体が動かないとき、意欲が出ないときは「なんとかなるさ」とつぶやく
た 楽しいことだけを考えて、とことん遊ぶ。どうせ死ぬんだから
学んだこと
→自分の親ががんになってから、人生やキャリアについていろいろと考えるようになりました。
“自分の心と体の声をしっかり聴いて、10年後に生きていられるかどうかわからないから、
やっぱり旅行に行こうとか、これだけはやっておこうとか、そういうふうに考えると、死ぬまでの生活をより濃厚に楽しめる。“
誰しも10年後生きている保証がないということもあるので、
やりたいことはすぐにでもやるという考えは常に持っていきます。
「迷ったらやる!」ぐらいの勢いでいることがいいのかもしれないと思いました。
そして子ども達が小学生になるまで、成人になるまで、結婚するまで、子どもが生まれるまで、私が生きている保証はないと改めて気づきました。
そのため自分の家族や妻や子ども達にも、自分自身の人生で学んだことをブログで残していき、日々の言動や行動で伝えていきます。
自分の祖母や祖父がどのような考えで人生を歩み、子育てをしてきたのか・・・
今はすでに亡くなってしまっているので、聞くことは出来ない。。。
そのためそのような考えを知りたいと思っても、知ることができない”もどかしさ”のようなものを感じてました。
私自身は何か生きた証を残そうと思っております。
このブログが将来、生きる上で悩んだ時に少しでも参考になればとても嬉しいです。
この度も最後までお読みいただきありがとうございました。
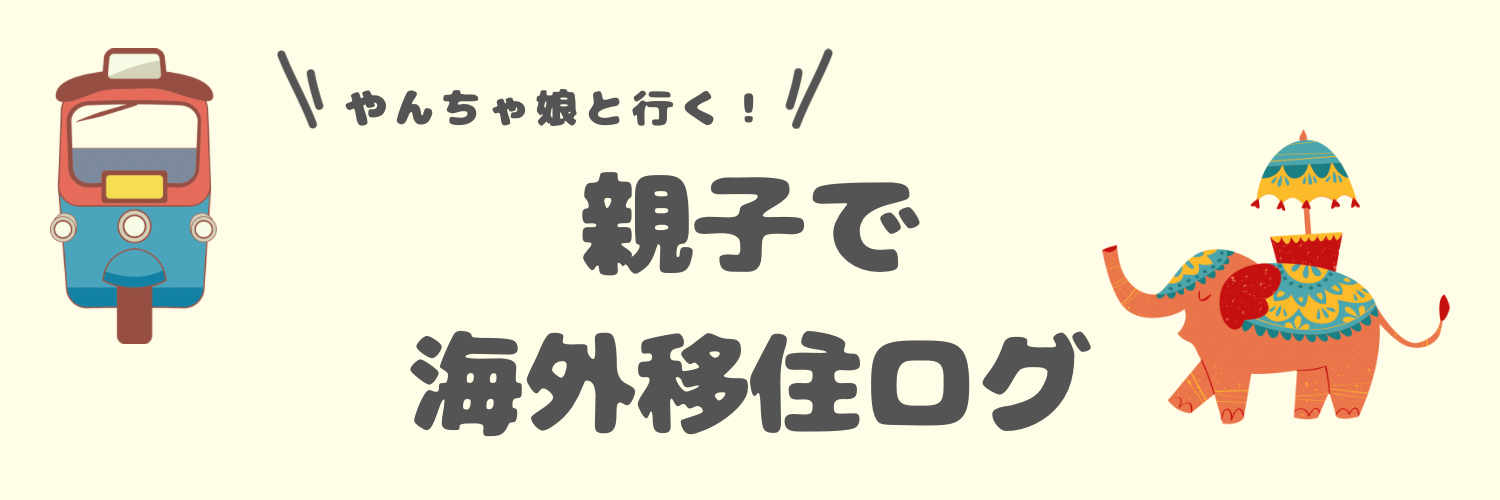



コメント